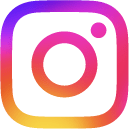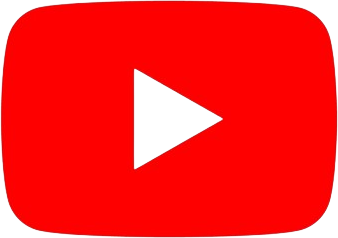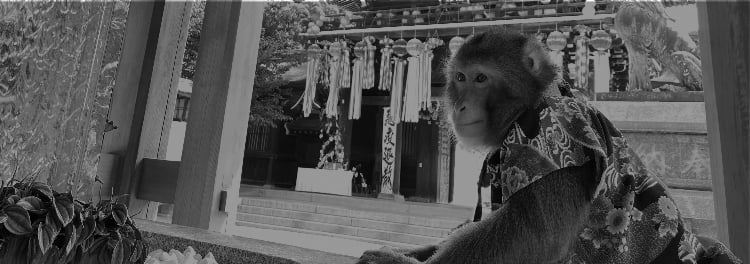二助企画と猿まわしの歴史
猿まわしは、日本の伝統芸能のひとつとして今日まで楽しまれています。その歴史は古く、遡ること1000年以上といわれます。
古来より猿は神様の遣いとされ、牛や馬を守る「まじない」として猿の舞が生まれました。災いがサル(去る)、病気がサル(去る)など厄除けの力があると信じられ、江戸時代には幕府専属の職業として確立したとも言われています。
猿まわしは一度、存亡の危機を迎えます。江戸幕府の解体に伴い大きな後ろだてを無くし衰退、更に道路交通法の取り締まりにより大道芸としての活動も難しくなります。追い打ちをかける第二次世界大戦でいよいよ娯楽は影を潜め、一度は忘れられた存在となりました。
しかしその中でも記憶に留め、伝統を絶やさぬようにと願い、戦後の復活まであきらめずにタスキを繋いだ人々の心が猿まわしの歴史には刻まれています。

私たち株式会社二助企画は、その歴史と思いを未来へ受け継ぐ為に、従来のような路上公演だけではなく、常設劇場を構え、依頼公演、TV、CM、映画出演など、芸能の分野で大きく発展いたしました。
お猿さんの技のクオリティはもちろんのこと「あきらめない気持ちが大切」をテーマに、話術、音響、衣裳、道具にもこだわった総合的な演出を行っております。そして、トレーナー育成にも力を入れ、この芸能の伝承に貢献したいと考えています。
言葉の通じないお猿さんと人間が互いを理解し合い生まれた信頼関係、そしてあきらめず挑戦する姿は、 「親と子」「友達関係」「上司と部下」など様々な人間関係を連想させるとともに、誰かに説明されるよりも素直に心の奥に残るものとなります。

いにしえの想いを、未来につなぐ
-猿まわしの歴史-
猿まわしの歴史はとても古く、日本で確認される文献上の初見は、13世紀に鎌倉幕府が編纂した歴史書「吾妻鏡」に書かれた猿舞の記事。一方で、絵画上では後白河上皇の要請で1165年に成立した「年中行事絵巻」の中に、猿を連れた猿まわしが描かれています。
猿まわしは元来、悪魔払いや厄除けといった神事でした。古来より猿は神様の遣いとされ、牛や馬を守る「まじない」として猿の舞が生まれました。かつての人々は、災いがサル(去る)、病気がサル(去る)など、猿に厄除けの力があると信じていました。江戸時代には、猿まわしが幕府専属の職業だったという記録もあります。日本の古典芸能のひとつである狂言には、「うつぼざる」という猿まわしが出てくる代表的な演目も。猿まわしは、長い歴史の中で、日本人の暮らしにとって親しみのある存在でした。
時代の流れと共に宗教性が薄まり、大道芸として楽しまれるようになった猿まわし。昭和初期には、道路交通法による取り締まりが強化され、大道芸としての活動も制限されてしまいました。追い打ちをかけるように第二次世界大戦の影響で、一度は忘れられた存在に。しかし、その中でも伝統を絶やさぬようにと、戦後の復活まであきらめずにタスキを繋いだ人々の心が、猿まわしの歴史に刻まれています。

二助企画の「猿まわし」
ものごとを極める段階として「守・破・離」という考え方があります。師や流派の教え・型・技を忠実に守り、体得する「守」。他の師や流派の教えについても考え、良いものを取り入れ、心技を発展させる「破」。身に付けた型から離れ、独自の新しいものを生み出し確立させる「離」。
私たち二助企画は、先輩方からの教えを「守」り、受け継がれてきた技術を習得した上で、ダンス、手話、音楽など、それぞれの持ち味を活かす「破」の段階で奮闘する日々。話術、音響、衣裳、道具にもこだわり、二助企画ならではの「離」の猿まわしを追求しています。

あきらめない気持ちが大切
それぞれの個性を活かした、新しい猿まわしに挑戦する私たち。その心にはいつも「あきらめない気持ちが大切」という信念を掲げております。
言葉の通じないお猿さんとトレーナーが一緒になって、お客様に芸を披露するために、一番大切なのは信頼関係。互いに諦めずに挑戦する姿は、「親と子」「友達関係」「上司と部下」など様々な人間関係を連想させるとともに、見る人の心の奥に残るものとなります。
猿まわしの歴史的背景に敬意を払い、伝統芸能の担い手としての誇りを胸に。
お猿の"えん"はご縁の"えん"
驚きと笑顔に満ちた感動のステージを、ぜひお楽しみください。